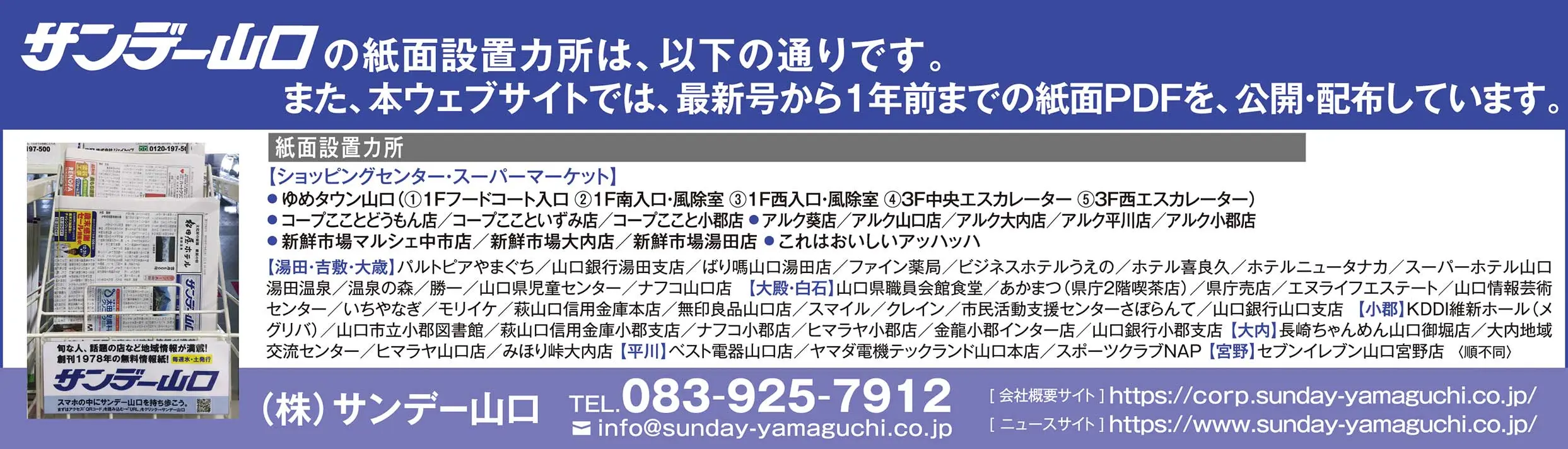「毛利輝元公没後400年記念イベント」が、4月27日(日)に、萩市の萩城跡指月公園(萩市堀内)をメイン会場に開かれる。
毛利輝元は、1553年(天文22年)に毛利隆元の長男として生まれた。祖父は、1557年(弘治3年)に大内義長を討って大内氏を滅亡させ、その後中国地方一帯を傘下に収めた毛利元就だ。 輝元は豊臣政権下において、安芸・周防・長門・石見・出雲・備後・隠岐7カ国および伯耆(ほうき)3郡と備中半国で112万石の知行目録を与えられ、1597年(慶長2年)には五大老に任じられた。だが、1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いで西軍の総大将となり敗戦。戦後、徳川家康から周防・長門両国に減封され、萩の地へと移り住んだ。1604年(慶長9年)、萩の指月山麓に萩城を築城。そして1623年(元和9年)、正式に長男の秀就に家督を譲り、2年後の1625年(寛永2年)4月27日に病没した。享年73(満72歳)。
このイベントは、「輝元公が萩に開府して以降260年余り、萩は毛利36万石の城下町として発展し、幕末期には近代日本の夜明けを告げた人々を輩出する明治維新胎動の地ともなった。萩市は、萩城下町や松下村塾など、世界遺産『明治日本の産業革命遺産』の五つの構成資産や文化財施設、歴史的な町並みを随所に保存し、まちじゅう博物館として全国に名声をはせている。これはひとえに、輝元公の萩開府があったからこそ」とし、「生前の偉業を広く知っていただくこと、またその功績を長く後世に伝えること」を目的に、さまざまな催しが繰り広げられる。
午前9時、毛利輝元公の墓所である天樹院墓所(萩市堀内)で墓前供養祭・神事が執り行われる。
同時刻、大名行列の「平安古備組(ひやこそなえぐみ)」も菊屋家住宅(萩市呉服町1)をスタート。この行列は、1720年(享保5年)に藩主・毛利吉元が金谷天満宮(現金谷神社、萩市椿)の社殿を修復した際、秋の祭礼時に備立行列を奉納するよう平安古町らの住人たちに命じたのが始まり。盛衰・廃復ある中でも約300年間続けられており、用具や調度品は藩主から下げ渡されたものを今も使用している。「イサヨ~シ」の掛け声とともに次々に毛槍を投げ渡し、道具類の持ち手を交代しながら、城下町から萩城跡へ向けて練り歩く。「草履舞」と「長州一本槍」は、菊屋家住宅前、萩博物館前(萩市堀内)、毛利輝元公銅像前(同)、萩城跡指月公園入口前で披露。11時には、公園内ステージでも実施される。
ステージイベントは午前10時から。御船謡 (住吉神社御船謡保存会)、平安古備組、空手・棒術・居合等日本武道演舞(田端隼人さん)、大板山たたら太鼓、萩民謡男なら(男なら保存会)、萩西中吹奏楽部、萩高吹奏楽部、萩光塩学院書道パフォーマンスなどが披露される。正午からと、午後4時の閉会前には、もちまき(約2000個)も実施される。
他にも、「花江茶亭呈茶席」「指月山トレイル」「出張はぎマルシェ」「子供縁日」などの催しもある。
さらに、この日だけの「毛利輝元公四百年祭特別限定御城印」(500円)も、200枚限定で販売される。
主催する同実行委員会は、「城下町『萩』の礎を築いた毛利輝元公が亡くなられてから400年の節目に、萩藩毛利家とゆかりのある伝統行事、10周年を迎えた世界遺産・萩城下町にある学校の生徒による吹奏楽の演奏やもちまきなど、市民みなで盛り上げていく。ぜひ、萩城跡指月公園で一緒に楽しんで」と来場を呼び掛けている。
問い合わせは、萩市観光協会(TEL0838-25-1750)へ。


 山口のニュース
山口のニュース

 前後の記事を読む
前後の記事を読む